
この記事をご覧になる方は、きっと宅建士(宅地建物取引士)に興味がある方でしょう。 そして「不動産業界の経験や知識もないけれど、独学でいけるかな?」と少し不安を感じていらっしゃるはず。
宅建は知名度の高い国家資格で、2023年に実施した試験の合格率は17.2%。簡単な資格とは言い難い試験です。
しかし、宅建は独学でも合格できます!
そこで今回は「宅建に挑戦してみたい」「独学で合格したい」と思われている方に、初心者が宅建を独学で勉強するためのタイパ・コスパ最強のテキストや勉強法について紹介します。
初心者でも宅建の独学は無理じゃない!
宅建試験の合格率は、ここ10年で15~17%台です。5人に1人も合格できていない計算になります。
「やっぱり初心者で独学だと無理なのか…」と思うのは、ちょっと待ってください。
この合格率は、実際はもう少し高い可能性があります。
というのも、宅建士とは、宅建業者の事務所ごとに必ずいなければいけない必置資格。当然、不動産関連の会社では宅建取得を推奨もしくは義務付けているケースもあります。その場合「あまり勉強していないけれど会社命令だし、とりあえず受験するか」という人が多くなり、その分合格率が下がってしまうのです。
それに宅建の試験は、満点を取るつもりで勉強する必要はありません。合格に必要な合格基準点は年によって違いますが、50点中31点~38点。50点中40点取れるくらいまで持っていければ十分合格圏内です。
また「受験生は不動産業界の人が多いのよね?なら、業界経験のない自分は不利だよね…」と思うのも、まだ早いですよ。
2023年の結果を見ると、宅建合格した人のうち不動産業の方は35.2%でした。金融業や建設業の方は各8%ほど、他業種の方は25%、学生10.9%、主婦4%、その他7.9%とさまざまな方が受験し、合格しています。つまり不動産業に関係なくても合格できるというわけです。
確かに宅建試験では難問も出題されます。ですが、頻出問題を理解して落とさないようにすれば、必ず合格圏内に入ります。
では、初心者が独学で宅建合格を勝ち取るのに役立つテキストと勉強法を見ていきましょう。
宅建初心者の独学に役立つおすすめテキストとは
宅建初心者が独学でありがちなのが、分厚いテキストに一から取り組み、専門用語や権利関係のわかりにくさにつまずいて勉強が嫌になってしまうこと。
不動産業界での実務経験や知識がある人なら、テキストはほぼスルーで問題集をメインに勉強するという手が使えますが、宅建初心者の方にはこの方法はおすすめできません。
ちなみに宅建では宅建業法や民法、借地借家法、都市計画法など法律の知識も必要です。そのため法務関連の実務経験や知識が無い方も、最初から問題集に取り組む方法はおすすめできません。
宅建初心者がまず始めるべきは、宅建の出題内容がポイントを押さえてまとまっている、入門の位置づけのテキストを最初に読み、基本を押さえること!そうすると、わかりにくい専門用語に慣れることができるのです。
それでは宅建初心者の独学におすすめのテキストを見ていきましょう。
おすすめテキスト「宅建士 超速マスター」
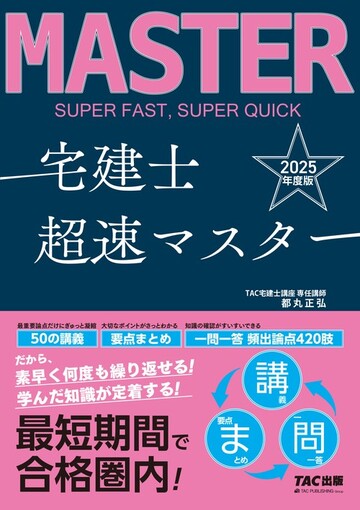
テキスト「宅建士 超速マスター」の最大の魅力は、短期間で基礎から試験本番にも対応できる実力を身に付けられ、その実力を効率的に引き上げてくれることです。
また、試験直前にも見直しやすいように超コンパクトタイプのテキストになっています。だから携帯しやすく、いつでもどこでも勉強することが可能です。
テキストの魅力をさらに詳しく解説していきます!
<テキストの魅力>
◆1週間程度で読み終えることができる量
◆講義形式で読みやすい
◆理解度を深めるヒントがある
◆絶対押さえたいポイントをまとめてくれている
◆一問一答あり
宅建の問題に出てくる専門用語や難解な部分は、テキストではわかりやすい言葉にかみくだいて表現されているので、とにかく初心者にも理解しやすいです。
宅建合格に必要な部分だけを抽出して作られているので無駄がなく、読むのが速い人なら1週間程度で読み終える量で構成されています。
内容も講義形式になっているので読みやすく、理解度を深めるようなヒントが随所に散りばめられているのが特長です。
また、絶対に押さえておきたいポイントは「要点のまとめ」や「講義のまとめ」として記載されているので、「あれ?どういうことだったかな」というときもすぐに復習できます。
どんなに優れたテキストでも、読むだけではなかなか頭に定着しませんよね?そこで「宅建士 超速マスター」では講義の最後に一問一答を掲載。しかも試験で頻出の論点や知識を問うものばかりなので、インプットとアウトプットが同時にできるのです。
このテキストを繰り返し勉強することで、理解度が高まり試験にも対応できるようになるでしょう。
わかって合格る宅建士 過去問12年PLUS〈プラス〉
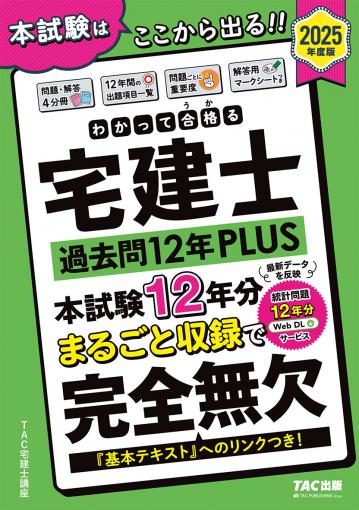
「宅建士 超速マスター」である程度知識を得たら、実践問題にも取り組む必要があります。宅建の試験では、過去の問題と似た問題が出やすい傾向に。だから過去問題集を徹底的に取り組む、しっかり理解することができれば合格圏内も夢ではありません。
そこでおすすめしたい実践演習のテキストは「わかって合格る(うかる)宅建士 過去問12年PLUS〈プラス〉」です。
年度別12年分の過去問が網羅されています。しかも、どれも法改正に対応して最新データで作り直してくれているので、過去問題であっても今の問題として問題を解くことが可能です。
また各問題に3種類のアイコンがあり、どの問題を確実に解ければ合格できるのかをひと目でチェックできます。だから効率的に勉強できるのです!万一問題がわからず行き詰ってしまったら、「宅建士 超速マスター」と対応しているので、すぐに確認できますよ。
年度別12年分となると、かなりの分量です。しかし、問題2冊・解答2冊にわかれているので、持ち運びも楽ちん。カバンに入れておけば、いつでも都合の良いときに勉強できますね。
宅建試験の問題は四肢択一。勉強を始めると「2つの選択肢まで絞れるけどどっちかな」と悩む方も多いはずです。もちろん解答編では丁寧な解説文があるので、何がどう違うのかまで一問ずつしっかり確認することができます。
宅建試験ではなんとなく解いてはいけません。「ここが違うから×」など正しい知識を持って取捨選択しなければ正解を導き出せないのです。
「宅建士 超速マスター」でインプットして「宅建士 超速マスター」でアウトプット。わからない部分が出てきたら「宅建士 超速マスター」で復習というサイクルができたら、宅建合格も目前ですよ。
宅建初心者が独学するために必要な勉強期間
では、実際に独学で宅建試験に合格するには、どのくらいの勉強期間が必要なのでしょうか?
宅建士である私の友人に独学での勉強期間を聞いたところ「1ヵ月」とのことでした。しかし、彼は不動産会社のバリバリ現役の営業マン、しかも受験3回目での合格なので初心者の方はあまり参考にしないほうが良いでしょう。
一般的には、宅建合格に必要な勉強時間は約300時間と言われています。毎日2時間勉強すると約5ヵ月かかる計算です。
しかしテキストや問題集を厳選して効率的な勉強をすると、不動産業界未経験者でも独学で、約3ヶ月で宅建合格する方もいます。空き時間を見つけて、どれだけ集中して勉強できるかが勝負です!
宅建初心者が独学で勉強する際のポイント
「オンスク.JP」では、宅建試験の各章ごとの勉強法についてまとめた記事があります。勉強を始める前にぜひ一度目を通してみてください。
【6月からの勉強スケジュール付き】宅建合格者が教えます!科目別勉強法①
「宅建業法」重要論点と勉強ポイント |科目別勉強法②
「民法等」重要論点と勉強ポイント |科目別勉強法③
「法令上の制限」重要論点と勉強ポイント |科目別勉強法④!
「税・その他」重要論点と勉強ポイント |科目別勉強法⑤
試験直前期の科目別論点&やるべきこと |科目別勉強法⑥
また、参考にしていただきたい連載もあります。
実は、試験直前の9月・10月あたりで、初心者の方は以下のようなトラップに陥りがちです。
「手持ちの問題集を半分もクリアしていないのに別の問題集に手を出し、結果として両方中途半端に」
「細かいところまで手を広げすぎて頻出問題を押さえきれないままタイムアウト」
前述しましたが、宅建は7~8割得点できれば合格圏内に入れます。7割得点するには、頻出問題を確実に解答できるようにしておくことが必須です。
逆を言えば、過去問を解いてコンスタントに7~8割解答できるのであれば、それ以上細かい部分まで手を出す必要はありません。
以下の連載に、宅建勉強のしくじりポイントが述べられているので、勉強中に「なんだか上手くいかないな…」と思ったらときどき読んでみてください。

最初に言いましたが、宅建試験の勉強は初心者でも独学でも可能です!
なによりも優先すべきはテキスト選び。
効率良く勉強できて解説がわかりやすいものを選ぶようにしましょう。自分に合ったテキストを選んで、今回の記事を参考に勉強スケジュールを組み立ててみてくださいね。
参考URL:
https://tacpub.jp/list/detail.php?bc=111451
https://tacpub.jp/list/detail.php?bc=111441
無料でオンライン資格講座を体験しよう!
オンライン学習サービス「オンスク.JP」では、70以上の資格講座が受け放題の「ウケホーダイ」プランをご提供中!
簡単な会員登録で、講義動画・問題演習機能を無料体験できます。ぜひお試しください!

関連する記事が他にもあります


